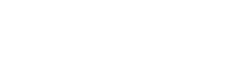東京大学への入口
こんにちは。東京大学理科一類1年のT.D.です。
私は小学3年生の附属小のころから青山ゼミに通っており、今年、現役で東京大学に合格しました。これまでの受験生活を通して私が得たことが後輩の皆さんやその保護者の方々の役に少しでも立てられればと思い、この合格体験記を書かせていただきました。
ここでは、私の青山ゼミの活用法、私の受験について、後輩へのアドバイスについてお話しします。
これまでご指導いただいた青山ゼミの先生方に、心より感謝申し上げます。
ゼミでの受験勉強について
中学受験
小6の10月に友達が久留米大学附設を目指しているということを耳にし、一緒に行きたいからという理由で自分も受けることにしました。今でも、あの時期に中学受験をしようという行動を取ったことに驚きを隠せません。その時までは中学受験の対策を全くやっておらず、直前までの附設模試は当然E判定であり、過去問で1回も合格最低点を超えたことはありませんでした。
ほぼ不合格確実だった私を青山ゼミは見放すことなく精一杯サポートしてくれました。
朝早くから夜遅くまで年末年始でも関係なくゼミを開けて勉強させてくれました。
詳しくは、青山ゼミホームページに当時の合格体験記を掲載していただいています。ぜひご一読ください。
附設中学に入学して実感したことですが、中学受験はするべきだと思います。
中高一貫校は6年でカリキュラムが組まれていることが多く高校受験がないため、着実に大学受験に向けての勉強が可能となっているためです。
私はやはり久留米大学附設は、一番入学に値する学校であると思います。
九州の中でもトップクラスの生徒が切磋琢磨しながら勉強する、福岡市の学生が家から通える学校です。
とはいえ主なデメリットは立地だと思います。久留米はさすがに遠すぎますね。
それでも、通う価値が十分にある素晴らしい学校です。
中学入学以降
私は附設中学に入学して以降、青山ゼミの個別指導を受講していました。
そこでは主に数学の未履修の内容や質問したい問題の勉強をしていました。
青山ゼミの先生の解説は非常に分かりやすく、おかげさまでずっと成績で上位をキープすることができました。青山ゼミの個別指導担当以外の先生方も、最後まで変わらず応援してくださっていたのが嬉しかったです。
大学の合格報告をしに行った時の先生方の驚きと笑みを今でも覚えています。
私が小さいころからずっと応援してくれていた青山ゼミには大変感謝しています。
小学3年生の時からの長い間、ありがとうございました。
附設での生活
中学入学から高2まで
正直に申しますと、中学高校での私は定期テストで良い点を取れるように頑張って勉強していただけでした。中学受験で逆転合格して手に入れた環境を無駄にしたくないという意識があったからだと思います。自分よりも賢い友人にテストで勝とうという目標を持って努力したこともまた成績が上がった要因の一つだと思います。
やはり附設生というだけあって皆が頭いいのですよ…ちょっとでも勉強したら彼らはすぐ成績が伸びるのです。そのような賢い人たちに後れを取らないように勉強をしていたというのが真実だと思います。
部活は入っていませんでした。あまり学校に遅くまで居残りたくないという気持ちがあったからだと思います。今となっては何かをやっていればよかったと思います。
高3
以下が、私の平日の大まかな流れです。
朝5:50起床
6:08地下鉄に乗る
7:15学校到着、図書館で勉強
8:30始業
15:25終業
16:00特講開始
18:00特講終了、久留米大学の図書館に移動して勉強開始
20:20図書館を後にする
21:30帰宅、色々なことをする(勉強を少し)
23:20就寝
始業前の一時間は学校の図書館で自習していました。始業前に自習をすることを勧めます。当日する内容の予習やこれまでの復習を授業直前にすることができて効率的に授業を受けることができるためです。
附設には特講という7,8限に開講されていた授業があり、希望の大学の過去問演習をすることができました。大まかな流れとしては、最初の1時間で問題を解き、残りの1時間で解説を先生方がしてくださるというものです。個人的には予備校に行かずに無料でそのような授業が受けられたのは大変ありがたかったです。
特講の後は近くの久留米大学の図書館で自習することが多かったです。
私は家に帰ると遊んでしまうような人だったため、極力外で勉強して家では勉強しないということを心掛けていました。
休日には私は自習室を利用したり、自習スペースで勉強したりと様々な場所で自習していました。私の休日の勉強時間は10時間くらいだったと思います。私はそれが限界でしたが、この時間が皆さんにとって適切な勉強時間であるとは限りません。適切な勉強時間は人それぞれです。色々試して自分にあった勉強のルーティーンを見つけてみてください。
科目別の勉強法
国語
これは反省も込めてですが、古文単語や漢文の構文等をしっかり勉強しましょう。私は本格的に勉強し始めたのは10月くらいからでした。もっと前から対策すると、問題を解くのがより楽になると思います…。
私がしていた共テ対策として、選択肢を読むときはまず主語、次に文末を確認するということです。これは作問の都合上、一発で正誤判定ができる内容が選択肢の最後に配置されている傾向が高いからです。
また、「から(理由)」「つまり、すなわち(換言)」「例えば(例示)」といった特定の語にマーク印や傍線をつけることも有効です。解答要素の選別に大いに役立ちます。
数学
難しいことだとは思いますが、解法のパターン化をするべきです。
二次方程式の解の個数の条件を求めるときには判別式を使う、といった感じです。
これを全てに対して行うことで、大体の数学の問題はひらめきなしに機械的に解くことができるようになります。
附設の先生はこのように全てパターン化することで東大模試を機械的に処理しました。
【使用していた参考書1】「大学への数学(東京出版)」
高3の夏頃から使用。
月ごとにテーマが設定されており、学びたい題材を重点的に学べます。
有料ですが、学力コンテストという毎月開催されている模試形式の試験で自分の学力が測れます。東大模試で出題されてもおかしくない問題も含まれているため、難関大の受験生は解くべきです。
【使用していた参考書2】「入試数学の掌握(エール出版社)」
友人から勧められたので高3の春から。
東大、京大をはじめとする難関大受験生のための非常にためになる参考書です。
総論編、各論練磨編、各論実践編の三部作となっており、受験問題としてよく問われるが難解な問題の解法を丁寧に分かりやすく解説してくれる本。
そもそも取り扱っている問題が、多くの受験生が苦手とするような分野の問題であるため、書いてある内容を身に着けるのは困難ですが、一度マスターしてしまえば非常に強力な武器になるでしょう。
これは私の友人談ですが、各論実践編はほぼ京大志願者向けの内容で東大志願者等は買う必要があまりない、らしい。
【使用していたサイト】「受験の月」
大学受験に特化したウェブサイトです。化学の勉強にも使えます。
形容するなら「ゆりかごから墓場まで」でしょうか。共通テストの範囲をほぼ網羅し、二次試験の対策としても参考になります。
化学
暗記すべき事項を暗記して演習を重ねるということに尽きます。
【使用していた参考書1】「重要問題集(数研出版)」
【使用していた参考書2】「化学の新演習(三省堂)」
【1】は高2の時に使用。基礎固めから少し発展した内容の演習ができます。
【2】は高2の冬ごろから受験直前まで使用。問題量が多く、難易度もかなり高いため化学を極めたい人にはおすすめです。有機化学の構造決定の問題の種類が豊富であり、一歩踏み込んだ問題や思考力を問う問題が多数収録されています。
しかし、誤植が多いというデメリットも。買う時は必ず最新版であると確認して購入をお願いします。
物理
等号が等価を表しているのか、それとも因果関係を表しているのかという風に式の意味を理解しながら勉強すればよいと思います。
可能ならば最初から微積を交えた方法で解答すると良いかもしれません。
私は身に着けられなかったため微積物理の大学受験での恩恵を享受することがなかったためメリットはあまりよく分かりませんが、今大学生になって学ぶ物理の内容がほぼ微積を扱った内容であることから大学物理への移行がかなりスムーズに行えることからおすすめします。
ただし無理する必要はないと思います。
【使用していた参考書1】「重要問題集(数研出版)」
【使用していた参考書2】「標準問題精講(旺文社)」
【使用していた参考書3】「新物理入門(駿台文庫)」
物理の問題演習は【1】だけで十分だと思います。簡単な内容から難しい内容まで様々な問題が取り扱われています。
【2】は、タイトルに「標準」とありますが旧帝大や有名私立の問題が数多く掲載されています。
しかし解いてみると意外とシンプルな内容が多かった印象があります。
【3】は、ほぼ教科書です。微積物理を習得したい人にはおすすめです。
化学と物理に共通する勉強法ですが、ある程度基礎ができた後、私は参考書の問題がすべて同じ確率で選ばれるようなルーレットを用意して当たった問題を解くということをしていました。
これによって自分では進んで解かないような問題も強制的に解くことができ、すべての分野の演習をまんべんなくすることができます。
苦手な問題を自ら進んで解くことができないような人には勧めたい方法です。
若干遠回りにはなってしまうが、あまり嫌な気持にならずに演習ができると思います。
英語
私は高3の夏ごろまでは英単語を重点的に勉強していました。英単語は英文を読むときに極めて重要となる要素です。文法を知っていても単語を知らないと意味が取れません。
受験期に入ると、他教科や問題演習に追われて単語学習に十分な時間を確保できなくなります。そのため、受験期より前の早い段階から勉強しておくことを強く勧めます。
加えて、最近特に求められているのが速読力です。
時間に追われることの多い大学受験では速読力が合否に大きく影響を及ぼします。英単語と同様なるべく早い時期から何かしらの形で日常的に英文に触れておくべきです。私のおすすめは英語のニュースサイトを使った学習です。毎日新しい記事が更新されるため、飽きることなく継続できます。また、内容も多岐にわたるため、英語の学習と世界情勢を知ることができるのは一石二鳥だと思います。
【使用していた参考書1】「出る準パス単」
一番コンパクトに単語が載っていると思います。
可能ならば準一級を少なくとも高2までに、一級を高3の夏から秋にかけての時期に終わらせていたほうが良いというのが私の本音です。ハードルは高いと思いますが、皆さんならできると信じています(とはいえ一級までできたらすごいと思います…しかし意外と試験に出るので、やる価値はあると思います)。
余談ですが、「出る準」は今は5訂版が販売されていますが、私は勉強する際には4訂版で勉強することを勧めています。4訂版と5訂版で掲載されている単語の難易度に大きな差があるためです。基本的に4訂版により難しい単語が掲載されています(体感として5訂版の準一級は4訂版の2級と準一級の中間くらい)。
【使用していた参考書2】「Vintage(いいずな書店)」
【使用していた参考書3】「チャート式新総合英語(数研出版)」
どちらも英文法書。学校で使っていました。Vintageは散々な言われをされていることがあるのですが、個人的には悪くない本だと思います。句動詞がかなり詳しく掲載されており、一つの内容に対して一つ例文が問題形式で載っているところがいいと思う点です。
チャート式のほうはコンパクトにまとまっていて、読みやすくてよかったです。
【使用していたサイト】「Scientific American」
英語のニュースサイトです。毎日英文に触れたいとの思いでこのサイトを使い始めました。
高3の時は毎朝30分西鉄電車の中でGoogle翻訳を片手に読んでいました。
専門用語や入試には問われない単語が頻繁に出てくるため受験勉強にはあまり向いていません。その一方で、面白い科学の記事が多数掲載されているため、息抜きに読んでみるのはいかがでしょうか。
受験勉強にはCNNがおすすめです。友人は好んでこのサイトの記事を読んでいた気がします。
リスニングはBBCの6 Minute Englishを聞くのがおすすめです。こちらは複数人の会話形式で番組が進行し、途中で英単語の解説も挟まるため、リスニング教材として良いです。
過去問演習
私は東大の過去問を数学は約30年分、その他の科目は25年分を赤本で解きました。
赤本は基本的に解説が簡素な印象があったので、詳しい解説や予想配点が知りたいならば鉄緑会の過去問の問題集を買うことを勧めます。値は張りますが、何通りもの解法が丁寧に載っているため、買う価値はあると思います。
問題を解き始めた時期としては国語が4月、数学が8月、理科と英語が10月でした。
特講で4月から過去問を解いてはいたとはいえ、案外この時期から過去問演習を始めても受験に間に合うかもしれないです。ただ、自身の勉強の進捗状況と今後の予定とを照らし合わせて過去問演習を始めたため、ケースバイケースです。そのため、いつから演習を始めるべきかについては一概には言えないです。
受験について
共通テスト
終始とても緊張したことを今でも覚えています。
受験生にまず知っておいていただきたいことは、本番は試験と試験の間の時間が意外と長いということです。そのため、集中力が切れないようその時間をどう過ごすかについて考えておいてください。私は友人と雑談したり、一緒に最後の詰込みをしたりして過ごしていました。
もう一つ、絶対にしてはならないことがあります。試験が全て終わるまでは、終わった科目について友人と一切話し合わないということです。本番で私は友人に頼まれて数学の問題の解説をし、自分の間違いに気づいて絶望しました。あれは流石に心に来ました。たとえ友人に頼まれても心を鬼にして断ってください。そして初日のテストが終わったらその日あったテストについての内容を一切シャットアウトしておいてください。これも二日目に何かしらの悪い影響が及ぶことを防ぐためです。
二次試験
私はさあ東京へ向けて出発!という日に体調を崩しました。のどが痛く恐らく熱もあったと思います。
東京についてから薬を飲んだり安静に過ごしたりして頑張って体調を治そうと試みましたが治らず、直前の詰込みもできずにそのまま受験本番を迎えてしまいました。
迎えた初日、私は体調不良の中で国語を解かなくてはなりませんでした。特に頭痛がひどかったのを覚えています。体調不良で感覚が狂っていたのか、試験中は手応えを感じていましたが、結果は微妙でした。今年の国語は易しいセットだったため、あまり得点できなかったことへの悔しさが残ります。
試験が進むにつれて頭痛は次第におさまっていきましたが、その後の数学での手応えは満足のいくものではありませんでした。直前までスランプに陥っていたことに加え、今年出題された問題が難しかったためです。全ての大問で部分点を半分以上は取るような解き方をすることになり、結果も半分程度。今年の問題の難易度を考慮すると悪くない結果だったかもしれません。
二日目。体調はまずまずだったものの、理科、特に得点源のはずだった化学で新傾向の問題が出題され撃沈しました。約5分間、何も書かずに思考停止していたタイミングがあったくらい何も手が付きませんでした。それほどまでに今年の問題は難しかったです。正直、このあたりで浪人を覚悟しました。(私の大学のクラスメイトも解いていて生きた心地がしなかったそうです。)
そして二次試験最後の科目の英語。完全に心が折れた状態でしたが、「東大では総合点で合否が決まる」ということを意識して心機一転、気持ちを立て直し、模試の感覚で普段通りに解きました。その結果、普段と同じように解くことに成功。これまでの悪い流れを断ち切り、普段通りのパフォーマンスを出すことができました。
東京大学について
東京大学は日本初の近代的な国立大学であり、現在では国内外から高い評価を受けています。
東京大学は主に本郷・駒場・柏など、5つのキャンパスで構成されており、1・2年生は駒場キャンパスで教養学部前期課程を学びます。
特徴的なのは、入学時点で学部が確定していない点でしょう。
2年間の基礎教養を経て、成績に基づいて進学先の学部を決める「進学選択(通称:進振り)」制度が導入されています(詳細は後述)。
東大は、学問的自由度の高さと引き換えに、自律が求められる場所でもあります。自分で考え、選択し、行動する力を鍛えたい人には、非常に魅力的な環境です。
そもそも理一とかって何?どこに進学するの?
東京大学にはリベラル・アーツ教育の一環として教養学部前期課程(1~2年)があり、文科一〜三類、理科一〜三類の計6つの「科類」が存在します。
これらは学部とは違い、前期課程の学びの区分を表しています。前期課程では、各科類で専門に進むための基礎的な学習を幅広く行い、2年の終わりに「進振り」を経て、3年から本格的な学部での専門教育(後期課程)へ進みます。
各科類の主な進学先は以下の通りです。
・文科一類 → 法学部
・文科二類 → 経済学部
・文科三類 → 文学部・教育学部など
・理科一類 → 工学部・理学部など
・理科二類 → 農学部・薬学部など
・理科三類 → 医学部(医学科)
1,2年生はその自身が所属する科類で定められた後期課程での専門教育に必要な基礎的なことを幅広く学びます。前期課程に基礎教養科目を履修し終えた後は進振りを経て3年からの後期課程で進学した学部で専門科目を学びます。
定員は非常に限られていますが、全ての科類から全ての学部への進学も一応可能です。つまり、理科一類の学生が文系の学部に進学することや、その逆も可能であり、これは進振りの大きな魅力の一つでしょう。進振りは前期課程の成績をもとに行われるため、人気のある学部・学科に進学するためには高い成績が求められます。
この制度は柔軟で魅力的に見える一方で、東大生での「第二の入試」というのが実情です。希望学部学科への進学のために大学入学後もこれまでと同様に勉強を続けなければならなかったり、進振りに失敗すると希望でない学科に進学する可能性があったりと負の側面もそれ相応に持っています。
授業・時間割について
大学の授業は高校と異なり、自分で時間割を組むスタイルです。必修科目はあるものの、出席の有無も基本的には自由です。そのため、私の友人の中には、期末テストの日に初めて教授と顔を合わせたという人もいるほどです。
東大の授業は1コマ105分と長く、私はその長さに未だに慣れていません。1限は8:30開始と大学生にとっては早く、朝型だったはずの私も出席するのに苦労しています。1日の生活を全て自分で決めなくてはならず、その結果、今では生活リズムが崩れ気味です。私は高校生だった数ヵ月前と比べて起きる時間が約一時間半遅くなりました。
親がどれほど生活のサポートをしてくれていたのかを身に染みて感じています。
皆さんは、両親を今のうちから大切にしてください。いつかこのことが分かります。
サークル
東大には様々な面白いサークルが存在します。
うどん好きが集まるサークル、作問サークル、コスプレをするサークル等々...
そんな数あるサークルの中で私は東大洋弓部(アーチェリー)に所属しています。
サークルというか運動部になりますね。今は駒場で週二回、新木場という場所で週末に部の皆と練習をしています。今はまだ射形(弓を射るときの基礎となる部分)の練習をしているため本物の弓を射ることはまだできていませんが、実際に射る先輩の姿を見て早くあの人たちのようになりたいと夢見ながら練習をしている日々です。
東大の入試について
東大の合否は総合点で決まるため、どの科目で何点を取れば合格が確実とは一概には言えません。
しかし、理一での目安を私の感覚のもとであげてみることにします。一つの基準となれば幸いです。
・数学:60点台後半
・英語:70点台
・理科:1科目あたり30点以上
勿論これはあくまで目安であり、各個人の得意不得意、年度ごとの問題の難易度などによって大きく左右されます。私の設けた基準を超えたからと言って慢心せず、引き続き勉強に励んでください。
東大特有?の面白いところ
東大には「逆評定」と呼ばれる、学生が教授を評価するユニークな風習があります。これは教授が生徒の成績をつけるのに対して、「逆に我々も先生の成績を決めてやろう!」という発想から始まったものらしいです。
教授は「大仏」「仏」「鬼」「大鬼」の4段階で評価されます。
例えば「大仏」がついている教授だと単位を貰えやすい、教授が優しい等の評価がされており、この教授のする授業には人が集まりやすく、逆に「大鬼」がつくような教授だと単位が来にくい、教授が厳しい、課題が多すぎる等で誰もとりたがらず、といった感じです。
「大鬼」の教授が必修の場合は、その厳しさに耐え忍ぶしかない…ということになります。
東京大学は国公立大学の中で2番目に学生数が多い大学です。
ちなみに1位は大阪大学。大学院生の人数も考慮すると、東大が最大の在籍者数を持つ大学となるそう。
実は東京大学には校歌というものが存在していません。
そのかわりに応援歌と運動会歌と学生歌が存在しそれらが校歌みたいな扱いを受けています。
女子率が低い理系には全員男子のクラス、通称男クラが存在します。
理系では基本どの第二外国語をとっても存在します。聞いた話だと朝鮮韓国語のみ存在しないとか。
アドバイス
何を始めるにしても早いほうがいいですが、時に英語を小さいころからやっておくべきだと思います。
安定した得点が望めることと将来の仕事の幅が広がるといったメリットが大きいからです。
受験期でも適度の遊びと運動は大切です。
たまに外に出て運動をしましょう。
体育が授業としてある場合はこっそり参考書を持ち込んで勉強したりせず、しっかりその時間は遊びましょう。私は9月に運動不足により体調を崩してその余波が1カ月以上続きました。
共通テストと二次試験の両方にいえることですが、ちょっとのことでも手を挙げて試験官に報告することが大事です。
周りから注目されるのが恥ずかしいなどの理由で我慢して報告しないでいることよりも寧ろ試験中にそれに気を取られ続けた結果落ちてしまうほうが恥ずかしいです。
私は実際、共通テストの地理の試験開始直前に尿意を催してしまい試験監督に言ってトイレに行き、二次試験では私の席の隣がドアだったのですが、そのドアの隙間から空気の通る音が気になって試験官に対処してもらいました。
こういうのは周りの人の迷惑になるという余計なことを考えずに積極的に言ってください。
色々書きましたが、生徒の皆さんは適度の休憩を挟みつつ勉強に全力で励んでください。
明るい未来があなたを待っています。
高校での生活、大学受験関連の話題が多くなってしまいましたが、勉強を頑張るのは小学校、中学校と早いほうがいいです。
先述した通り、私は附設に入学してから難関大への距離が中学の段階で一気に縮まりました。
これを今読んでいる小中学生、勉強するなら今です。
今からでも十分間に合います。
青山ゼミで先生の言うことを聞いて全力で勉強してぜひ附設、東大に来てください。
お待ちしております。
最後に、この合格体験記を書くにあたり、私の思いを全力で書いたところ、気づけば約9,000字書いていました。「流石に長すぎや!」と言われましたが、そんな身勝手な振る舞いを許してくださった青山ゼミの先生方、本当にありがとうございました。
そして、最後まで私の長すぎる合格体験記を読んでくださった保護者の方々、生徒の皆さん、本当にありがとうございました。